あっという間に、5月になっていた。しかし、本日はまだ5月3日であり、4月の記憶は鮮明であるため、4月の振り返りブログを書いていく。食べ物の3秒ルールと同様に、ブログには3日ルールを持ち込むこととする。
(といいつつ公開日は5月5日になってしまった・・・)
4月のハイライトたち
- 入社!!!
- 編み物の世界にのめりこむ
- 会社のハッカソンで優勝
- ニコニコ超会議(&同窓会)
会社員生活の始まり
まず、避けられないのが会社について。3月までゆるゆる学生だった私が、ついに、フルタイムで会社勤めをすることになった。私は、高校は通信制(N高)だった上、中学は行ったり行かなかったりだった。また大学は毎日通う場所ではないことを考えると、フルタイムで1つの組織にコミットすることが、実に小学生以来。・・・小学生以来?!こういったブランクがあり、きちんと毎日仕事できるかは、少し不安であった。(今でも若干不安)
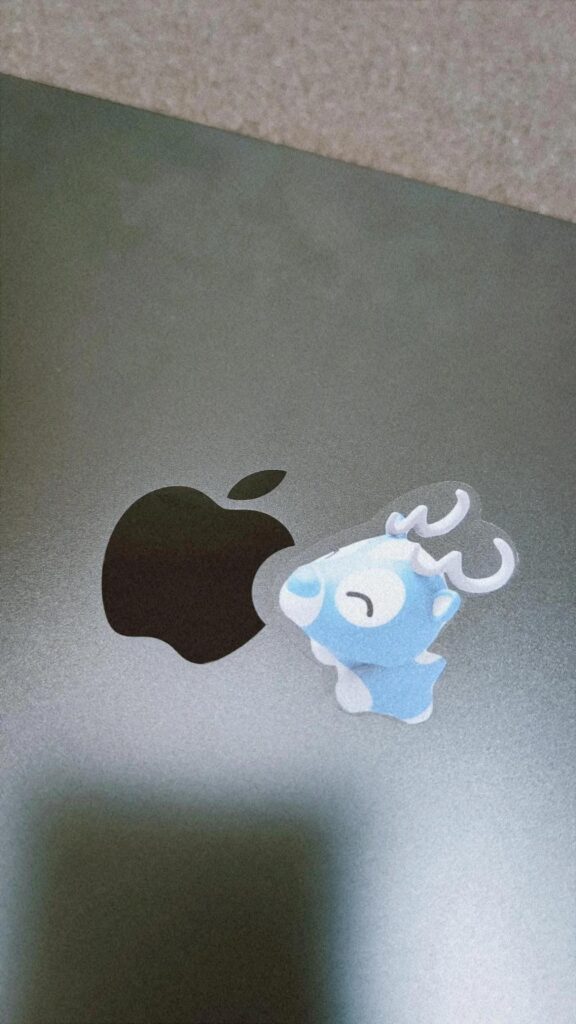
入社後、わずか一か月しか経っていないが、現在の感想としては「働くって楽しい!」と素直に思う。先月までの学生生活より、会社員生活の方が遥かに楽しい。
会社員生活の方が楽しいことには、様々な理由があると思う。ぱっと思いつくのは、2つ。まず第一に、会社では、努力に対して見返りが用意されている。例えば、毎週マネージャーと1ON1がある。そこでフィードバックをもらうことが多いのだが、自分の強みやよくやったことについて褒められると嬉しく、もっと頑張ろうという気持ちになる。また、毎月25日に振り込まれるお給料も、一か月の努力を肯定してくれるような気がする。もちろん、これから先、成果に結び付かない労働が発生することもあるだろうが、学生生活はそのようなことの繰り返しだったため、そのようなことには慣れている。言い換えると、仕事では脳の報酬系がよろこぶ刺激が用意されているため、若干の中毒性がある。
仕事が楽しい2つめの理由は、学びと応用が直結していることだと思う。ソフトウェアエンジニアという仕事は、ドメイン知識がなければ成り立たない。そして、そのドメイン知識を土台に、コーディングによって問題解決をする仕事だと思う。これは、学生時代の学習と研究(論文執筆)のサイクルに相当すると思うが、仕事における学習とコーディングのサイクルの方が、遥かに速く、スピード感をもって取り組める。これもまた面白いと感じる。
以上、会社員生活に対しての私のスタンスであった。会社についても少しだけ書いてみよう。会社について友達に話すと、決まって「外資だね~」と言われる。(本当に100%そういう反応を受ける。) そう言われる所以は、同期がおらず新卒は私しかいないことや、日本人が数人しかいないのでずっと英語を使っていることにあると思う。最近、仕事でも家でも英語を話すので、日本語に触れる機会が減ってしまった。(日本語が恋しくなったときは霜降り明星のオールナイトニッポンを聞いている。)
編み物
先月まで、ブログではその月に読んだ本を紹介してきた。なぜなら、私は毎月10冊以上の本を読んでおり、本は生活の中心だったためだ。しかし、今月はそのセクションがない。なぜか?今月は本を数冊しか読んでいないからだ!!!!では、なぜ本を少ししか読んでいないのか?社会人になって働いていると本が読めなく・・・・・・ではなく、ずっと編み物をしていたので読書時間が確保できませんでした。(読もうと思えば読めました)

というのも、こちらの本(編むことは力 ロレッタ・ナポリオーニ 著 佐久間裕美子 訳)を読んで以来、編み物の世界に再び引き寄せられている。編み物は昨年末から始めて、1月の入院中には心のよりどころとなっていた。改めて、本書を読むと、編み物の奥深さに魅せられる。名もない女性たちが、先祖代々編んできて、その技術を2025年にも自分の手で再現できる。これほど美しいことはない。
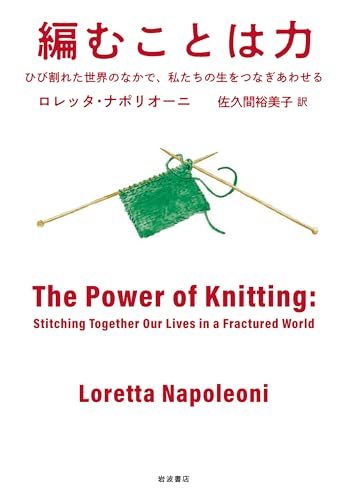
今月は編み物にハマったため、編み物に関する本をいくつか読んだ。編み手の歴史は本当に興味深い。時には戦争に行く男のためにニットを編み、また時には生まれてくる赤ちゃんのために編んだり、一方で、それが金銭的価値を生み出す労働だったときもある。「編み物」という手段があり、その手段の活用方法は社会によってひっくり返っていく。その意味で、編み物は社会を映し出すリフレクションだと思う。私が今大学生に戻れるとしたら、編み物で卒論を書いていただろう。実際に私は、祖母に電話をかけ、祖母が若かったときに「なぜ」「誰のために」編み物をしたのか聞きまくったときがあった・・・編み物のエスノグラフィーしたいですよね!!
近年の編み物ブームでは、「女性が自分のために編む」点が新しいと思う。私たちは、自分のために、自分がほしいマフラーを編む。

年配の方に「私は編み物が好きなんです」と言うと、「お父さん・彼氏にマフラーでも編んであげたら?」と言われたことがある。私は、そう言われたとき、びっくりしてしまい「なんでですか・・?!」というような反応をしてしまった。彼らから贈り物をもらったわけではないのに、どうして私が編み物を送らなければならないの?と、本当に混乱してしまった。私は、楽しいから編み物をしている。そして、私のような若い編み手が、Tiktok, Threads, Instagram、YouTubeのようなソーシャルメディアに加え、オカダヤ・ユザワヤをはじめとする都内の毛糸屋さんに、溢れている。(本当に文字通り「溢れて」いて、新宿オカダヤ本店に行くエレベーターは10分ほど並ばなければいけないときがある。)みんなさまざまな動機があると思うが、毛糸屋さんに行くと、自分が自分のために編む、新たな編み物の社会現象を感じる。
また、こうやって書いていると、モノで溢れた消費社会のことを考えずにはいられなくなった。私の祖母が若いころ編み物をしていた理由は、近所におしゃれな服屋がなかったからだ。彼女らが、代わりに家族の服を編んでいたらしい。消費社会で育った私には、「本当に必要なもの」を編む経験ができない。私が編むものの代わりは、いくらでも店頭に並んでいる。
北欧旅行の計画
編み物関連でもう一つ。6月に、会社の出張でエストニアへ行くことになった。仕事のあと、一週間の北欧旅行を計画している。デンマーク、フィンランド、エストニアへ合計一週間ほど滞在する予定だ。現地の編み物フェスティバルに参加し、色彩に関するワークショップに参加したり、現地の毛糸屋さん巡りをするつもりである。旅の目標はただ一つ、北欧の編み手と素敵なネットワークを築くこと。
ここまで、ものすごく長くなってしまった。会社のハッカソンで優勝した話と、ニコニコ超会議(&N高同窓会)の話は、気が向いたら書くことにする。・・・このノリだと、多分一生書くことがないので、もしも読みたいという方がいたら、教えてください。そうしたら喜んで書けるから!

コメントを残す